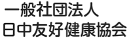このところ地球環境問題は深刻化する一方です。われわれの住む地球は海のお蔭で「青い惑星」とも呼ばれてきました。人類そのものも海から誕生したとされているほどです。ところが、その海が危機的な状況に陥っています。世界の気象並びに環境専門家によれば、海洋プランクトンが絶滅の危機に瀕しているというのです。このような状況が続けば、「海からの贈り物」を味わうことはできなくなるでしょう。
なぜなら、魚介類の食糧である海洋プランクトンがなくなれば、海洋生物は生き残れなくなります。必然的に、われわれ人類も生存が危ぶまれることになりかねません。こうした事態を引き起こしているのはわれわれ人間です。ゴミや汚染物質を平気で海に投棄してきたのですから。2023年春には、福島の原発事故で発生した放射能汚染水まで希釈した上で太平洋に放出することを日本政府は決めました。実に恐ろしいことです。
他にも恐ろしい事態は静かに進行しています。例えば、日中間の「のどに刺さったトゲ」のような尖閣諸島問題にも、最近は新たなスポットライトが当たり始めました。何かと言えば、“漂着ゴミ”問題です。この種の海洋汚染を放置すれば、周辺海域の環境が著しく悪化する可能性が高くなります。このことが、2022年1月末から2月頭にかけて行われた海洋調査によって明らかになりました。
この調査は石垣市の委託を受け、東海大学海洋学部の山田吉彦教授らが同大学所有の海洋調査研修船『望星丸』を利用して行ったものです。10年ぶりの尖閣調査でしたが、その結果、離島周辺の生物や漂流ゴミの実態が明らかにされました。当初は島への上陸調査を計画していましたが、所有者である国の許可が下りず、海洋調査のみが行われた次第です。
この調査が実施されている間、中国の海警船2隻が調査を妨害しようとし、無線等で「退去要求」を繰り返したようですが、海上保安庁の巡視船8隻が『望星丸』を警護し、離れた海域では海上自衛隊も待機していたため、目立った問題は発生しませんでした。そうして得られた現地調査の結果、水質や漂着ゴミの実態が把握されたわけです。
この問題は日本の国会でも取り上げられました。参議院の予算委員会で答弁に立った山口壮環境大臣は「海岸に漂着したゴミは、良好な景観あるいは海洋環境に悪影響を及ぼすことから、海岸漂着物処理推進法に基づき、海岸管理者がその処理のために必要な措置を講じること、あるいは土地の占有者が清潔の保持に努めること、とされている」と説明しました。
更に、山口大臣は「尖閣諸島に関しては、この海岸法に基づく海岸管理者が定められていない。現状では海上保安庁、財務省、防衛省が占有する土地となっている。その意味で、尖閣諸島における漂着ゴミを回収するためには上陸しなくてはならないが、この尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として政府関係者を除き何人も上陸を認めないという政府方針を踏まえなければならない」と発言しました。
同席していた岸田首相も「環境大臣が答えた政府の方針に基づき、政府としての取り組みについて考えていきたい」と曖昧な補足説明をするだけでした。要は、尖閣諸島における漂着ゴミの処理に関しては、具体的な対応策は未定というわけです。日本には海洋ゴミの回収、処理に関する技術の蓄積があるにもかかわらず、これでは「宝の持ち腐れ」と言っても過言ではありません。
というのも、この尖閣諸島問題はゴミ問題に飲み込まれようとしている以前に、日中間の領土問題化しており、日本政府としても政治的に慎重な対応を余儀なくされているからでしょう。日本がゴミ処理との名目で上陸するとなれば、中国政府の反発も予想されます。最悪の場合、中国が尖閣諸島を台湾の一部である自国領としていることから、日本の尖閣諸島上陸や周辺海域でのゴミ処理活動を内政干渉や領土侵攻であると見なし、中国側の武力行使の口実にされかねない恐れもあります。
その意味でも、「尖閣諸島の海洋ゴミ問題の解決」や「海洋資源開発」を進めるには、日中双方が英知と技術を持ち寄り、共同戦線を張るなど平和的知恵を使うことが求められます。元を正せば、島々も海洋資源も中国や日本が生み出したものではなく、地球という生命体が生み出した自然の産物、いわば人類の共通財産です。そうした地球上の環境を守り、貴重な資源を有効活用する上で、日中間の相互理解と協力関係が構築されれば、世界のモデルとなるに違いありません。
琉球の大交易時代に遡れば、尖閣諸島が琉球と中国の交易のための島として存在していたことに思い至るはずです。そうした歴史的理解に立てば、安全保障の観点とは別の、自然を守る「海の外交」という可能性を追求すべきではないでしょうか。われわれの健康を維持するためにも「海からの贈り物」は欠かせません。大事に育てる環境を忘れてはならず、放射能汚染水を海に流すことは、人類の生まれ故郷を破壊する行為に他ならないと思われます。今こそ、日中両国が国際社会に訴え、あらゆる英知と技術を結集し、海洋環境の保護に取り組む時ではないでしょうか。