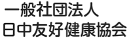日本では人口減少に歯止めがかからない。このままでは、21世紀の終わりには「地球上から日本人が絶滅する」との予測まで明らかにされている。とはいえ、平均寿命は延びる一方で、「人生100歳時代」は当たり前で、今や「120歳時代」もありうる話となりつつある。実際、100歳以上の日本人の数は年々増え続け、10万人の大台に乗りそうだ。世界が羨む「長寿大国」といえるだろう。そんな中、寝たきりの長寿ではなく、元気ハツラツな「健康長寿」を実現する上での健康法が関心を呼んでいる。
日本は健康関連グッズや書籍の数では世界ナンバーワンである。中でも、南雲吉則医師が提唱する「空腹健康法」は正に“逆転の発想”といえるかもしれない。実際、同氏の近著『「空腹」が人を健康にする:1日1食で20歳若返る!』は驚異的な売り上げ記録を達成。同医師は過去10年間以上、一貫して「1日1食」を実践してきているとのこと。自らの経験をもとに、「空腹」がもたらす健康上のメリットを明らかにしており、共感する読者の輪が広がりつつある。
実は、拙著『快人エジソン』(日経ビジネス人文庫)でも紹介したが、アメリカでも発明王トーマス・エジソンの時代までは「1日2食」が当たり前だった。電気を使った調理器具を開発し、その普及を目論んだエジソンは、「1日3食運動」を提唱。要するに、食事の回数が増えれば、調理用の家電製品の売り上げが伸びると判断したのであろう。宣伝を兼ねてアメリカ初の料理学校も設立したほどだ。
そのお陰で、エジソンが発明したトースターや電気鍋は爆発的な売り上げを達成したのである。アメリカ人はもとより世界の人々の食事の回数を増やすことに成功したわけで、エジソンは「マーケティングの天才」とも呼ばれるようになった所以である。
とはいえ、人間が生きていく上では1日3食にこだわる必要は全くない。日本も江戸時代までは1日2食が当たり前だった。そうした食習慣が大きく変わり、今では「体が必要としていない」にも係らず、「時間がきたからお昼にしよう」といった流れが世界的に定着している。
その結果、世界的に肥満人口が増え、却って寿命を縮めるケースが顕著になってきた。何しろ、世界の肥満人口は10億人を超えるといわれるほど。中でも中国の肥満率は半端ない。政府の統計でも、大人の半分は肥満と認定されているほどだ。しかも、COVID-19に感染した場合の重症化率や死亡率は肥満の場合には極度に高くなる。世界保健機関(WHO)によれば、1975年以降、世界の肥満人口は3倍に増えた。中東のカタールに至っては国民の70%が肥満と分類されている。
と同時に、世界では飢餓で苦しむ人々も10億人に達するといわれる。人道的観点から食料支援は欠かせない。自然災害やテロ、内戦の影響で難民の数も急増中である。これでは世界的に食料不足が深刻化することが避けられない。しかも、肥満も飢餓もどちらにしても健康にとってはマイナスな環境という意味では「同じ穴の狢」といえるだろう。食と健康をめぐる問題は、実に悩ましい限りだ。
そうした背景もあり、南雲医師に続くように、内海聡氏による『1日3食をやめなさい!』という啓発書が出版され、こちらも版を重ねている。内海氏によれば、「食べ過ぎこそが老化と万病のもと」。こうした一連の「食生活の見直し」ブームが起こってきた背景には、現代の医学的常識を再チェックする動きが医者の間でかつてないほど高まってきたことがあるように思われる。
健康を確保し、維持するには医療ではなく食生活が要(かなめ)という発想が生まれてきたのである。例えば、真柄俊一氏の著書『食は現代医療を超えた』などは、そうした観点から食生活の重要性に着目した啓蒙書である。こうした医療より食生活を通じて健康長寿を達成しようとする動きは日本に限らずアメリカやヨーロッパでも顕著になってきている。その意味では、健康維持の観点から食事を見直すのは世界的な傾向といえそうだ。
これは見方を変えれば、従来型の医学に対する挑戦に他ならない。医師や薬に健康維持を委ねるのではなく、日々の食生活のあり方(回数、食材、調理法、噛み方、食べる場所や雰囲気等)を自ら考えることで、自分に合った健康法を見出そうというわけだ。飲み込む前の噛む回数についても、現役最高齢の医者として105歳まで活躍された日野原重明先生は「飲み込む前に30回は最低噛むように」との指導をされていた。
医者である加藤誠氏の著した『医者に殺されない47の法則』も、過激なタイトルに象徴されるように、現代医学の限界や問題点を痛烈に批判した内容で医学界にも衝撃が走った。当然、医学界からは反論も出たが、患者の立場である読者からは「わが意を得たり」という積極的な反響が圧倒的であった。要は、「自分にとって最も頼りにできる主治医は自分だ」という認識が健康長寿への第一歩ということであろう。